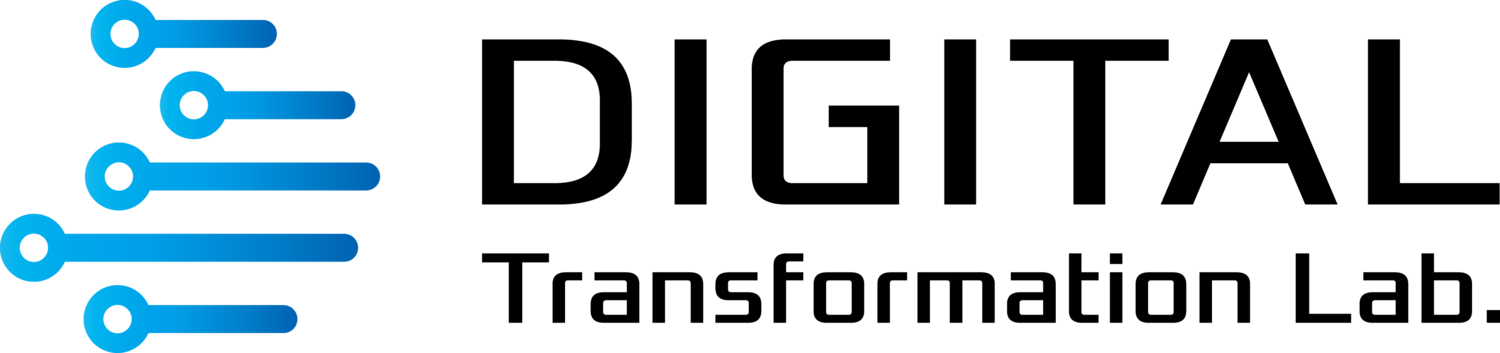DX研修年間100回実施、累積受講者10万人到達~2024年度のDX研修振り返り~
2025年度が始まりました。昨年度は、年間約100件の研修を企業や自治体にお届けすることができました。また、これまでの累積受講者数が10万人に到達いたしました。多くの方のご支援の賜物です。皆様に感謝申し上げます。
デジタルトランスフォーメーション研究所を起業した際は、DXという言葉をご存じの方もおらず、まして「DXを通じて日本の競争力を高める」をミッションとしながらも、それに対して、露ほども貢献できていない状態をもどかしくさえ思っていました。
しかし、多くの組織をご支援し、1社1社が今までできなかった価値創造や変革の成果が出始めており、「日本の競争力を高める」手ごたえも高まってきたと感じています。
より多くの組織のデジタル競争力を高めるために、内部の力だけでは実現が難しい組織変革のお手伝いを新年度も実行して参ります。
昨年度の研修事業の傾向について、研修成功のポイントなども交えて、以下に共有させていただきます。
2024年度の研修の傾向
デジタルスキル標準(経産省、IPA)
2024年度の大きなトピックの1つは、経産省(IPA)のデジタルスキル標準の更新(初版は2022年12月、その後順次更新)です。これは、多くの企業が社員のスキルを組織的に向上させる動機となりました。多くの企業では、「国が言っているくらいなので、うちもスキル教育をしなければ」という研修予算をとるための口実としては、都合がよかったのだと思います。結果的に、「ビジネスアーキテクト研修をお願いします」というニーズが急上昇しました。
ただ、ここで研修予算を積み上げて、人事部主導で研修や資格獲得などに走った企業の過半数が、目的を見失い、「いつ成果が出るのか?」と言った疑問を感じているのが実態です。ビジネスアーキテクト研修のご依頼の際は、「研修開催の目的や目標を教えてください」とお伺いするのですが、このうまくいかない過半数の企業においては、「年間500人です」などの数量的な目標しかなく、「DXで何を実現したいか」「どんな課題を克服したいか」などの具体的なテーマ設定がない場合が多い印象です。
DXは企業を変革し、その価値を高める手段であり、さらに研修はその手段の1つでしかありません。目的が示されていないDXや研修を乱発することは、組織の生産性をかえって妨げ、新しく得るものは限定的となってしまいます。ぜひ、変革で何を実現したいのかという目的を定義してから着手するようにしたいものですね。
DXリーダー研修
2つめの大きなトピックは、組織における実テーマを使って価値創造型DX企画の立案をするDXリーダー研修の増加です。どうせDX時代の価値創造スキルを学ぶのならば、事業で使える企画を考えようというグループワークを活用した欲張りなカリキュラムになります。ケーススタディやサンプルテーマと異なり、実際に組織として価値あるDX企画の立案ですので、参加者も気合が入る場合が多く、最終日は役員や社長の前でプレゼンするような大舞台も用意されたりします。また、成果も重視するため、必要に応じてメンタリングというグループごとの個別サポートを実施する場合もあります。
このDXリーダー研修をご依頼いただく部門ですが、以下の4パターンがあります。
人事研修部門
情報システム部門
経営企画部門
DX推進部門
驚くべきことに、どの部門からご依頼いただくかによって、そのDX研修やその組織のDXの状態がある程度推察できる面がありますので、その特徴について、少し触れさせていただきます。
人事研修部門
デジタル技術の習得などを目的とした他のスキル研修と同列に企画されていることが多く、「DXで何を実現したいか」という経営層の意思を十分受け継いでいない場合が多い
情報システム部門(IT部門)
組織変革という要素が重要視されるDXにおいてIT部門は適切ではないが、DXをIT分野の活動として会社が認識していること、DXの初期段階の組織であることが推測される
経営企画部門
中長期経営計画を担当する経営企画の活動の一環として会社がDXを位置付けている。DX時代にどのような経営戦略や事業戦略を実行するかという計画の一括立案が容易
DX推進部門
DX推進専門組織が発足し、DX研修を重要施策と位置付けている状態。DX研修の設計をDXの設計の一環として検討するため、具体的な成果につなげやすい。
DXリーダー研修には、スキル獲得優先の場合と、成果重視の場合があります。実テーマを使った成果重視研修には「成果最優先」という姿勢の企業もある一方、「スキル獲得が重視だが、よい成果が出ればラッキー」くらいの温度感の企業もあります。いずれにせよ、何かしらの実行可能な企画への落としこみを成果を期待する場合は、以下のような研修の外側の設計が重要となります。研修には、内側の設計と外側の設計が存在しますが、外側の設計は、研修を自社のDXや事業の中にどう位置付けて、戦略的に活用するかという重要な設計です。
テーマ選定
どのようなテーマを選定するかですが、せっかくよい企画になっても、会社の方針やDX基本方針とのギャップがあると実行できない企画になってしまいます。ここでは、DX基本方針、事業部方針などが整合性がとれている前提で、組織が重要視するテーマ(ないし分野)を選定することが求められます。
グループ編成
DX関連企画は通常複数の部門にまたがる関係者で進める必要のなるものが多いため、テーマに沿った各部門の連携が求められます。重要テーマに取り組み、具体的なDX企画を立案するグループワークですから、上司や事業担当役員がしっかり納得した上でのアサインをしたいものです。
修了後のプロセス
研修でよい企画を立案しても、それを評価し、先に進める判断をする意思決定の仕組みや、実践的に取り組む体制、課題を見つけて変革施策をとるDX推進部門の支援などがなければ、単なる研修で終わってしまいます。研修におけるグループ編成と実際に企画の遂行にアサインされるべきメンバーは多かれ少なかれ異なるのが通常で、「業務の片手間で企画実現に向けて努力せよ」と役員が講評してしまうと、何も実現できないばかりか、関係者のモチベーションを大幅に低下させてしまいます。研修後も継続的なアサインメントとして、企画取り組むことができる道を残したり、研修後から企画に参加する制度を用意するなど、組織にあわせた実行体制を研修前から構想しておくことは重要です。
経営層DX研修
3つめの大きなトピックは、経営層DX研修を実施させていただく機会が、2024年度に急に増えた点です。
経営層DX研修とは、「DXとは何か」「なぜ今DXが求められるのか」「自社をとりまく環境はどう変わるのか」「自社はどのような方向性の変革をしなければならないのか」を経営層の皆さまに集合研修形式で学んでいただき、自ら考え、組織の方向性を出していただきます。2-3回の開催を通じて、DXビジョンの骨子をアウトプットしていただく研修です。この研修が必要な理由は、経営層がリードするDXのビジョン(基本方針)がないまま、「DXせよ」と発信することは「(目的語なく)変われ」とだけ言っているのと同様であり、どう変わってほしいか、どのような戦略やビジネスモデルや組織行動を目指すのかがまったく不明のままとなるからです。DXのビジョンのないDX活動がまったく無意味とは言いませんが、現場の努力が報われず、日本でもっとも多くみられる失敗事例「空中分解するDX」になってしまいます。
この5-6年間、弊社は経営層DX研修の必要性を訴えてきましたが、「経営層を研修に出すなんて」という周囲や当事者の抵抗が大きく、実現が難しかったのが正直なところです。
しかし、2024年度においては、経営層主導のDXビジョンがないまま、数年間試行錯誤した企業が、ビジョンのないDXは成功しないということに確信した結果、多くの経営層DX研修の依頼をいただくことができました。経営層が全社視点で取り組むべきことを共通理解にし、自ら基本方針をアウトプットし、現場をリードできる状態になることほど、DXにおいて重要なことはありません。組織のDXが大きく加速する場面を多く目にすることができました。この傾向は、2025年度以降も強まっていくのではないかと期待しています。なお、2024年度は、DXのビジョンを立案しているうちに、途中から事業のビジョン立案プロジェクトや中期経営計画立案プロジェクトへ変化するプロジェクトも散見しました。DXのビジョン立案と、DXの要素を考慮して経営計画を立案することは、近いプロセスであり、最終的に整合性をとる必要があるため、当然の流れかと思っています。
自治体におけるDXサービスデザイン研修
自治体の場合は、国の後押しもあり、都道府県のみならず、市町においても、DX研修が増えており、DX時代のサービスデザイン研修を多く提供しております。参加対象としては、現場DXリーダー向けの場合と中間管理職向けの場合の2通りがある他、基礎自治体主導で、多くの地域の自治体が相乗りで研修を受けるケースもあります。ただ、スキル獲得にとどまっている場合が多く、研修の外側の設計まで実施できていることはほとんどありません。
自治体は、まだまだデジタル化に苦しんでいる段階が多く、本格的なDXに踏み込めているのは、東京都など人財豊富な行政に限られている印象です。ただ、従来の業務プロセスを部分的にデジタルに代替するにとどまることは、資本主義社会の中で日本という国が立ち遅れる原因にもなりますので、より積極的な変革が期待されます。行政においては、民間企業以上に従来の組織行動や組織構造などが阻害要因となっています。
我が国は、急激な少子高齢化や多くの社会問題を抱えていますので、多くの日本人が積極的に変革に取り組む環境を整えて、デジタル競争力を高める活動に参加いただけることを願ってやみません。