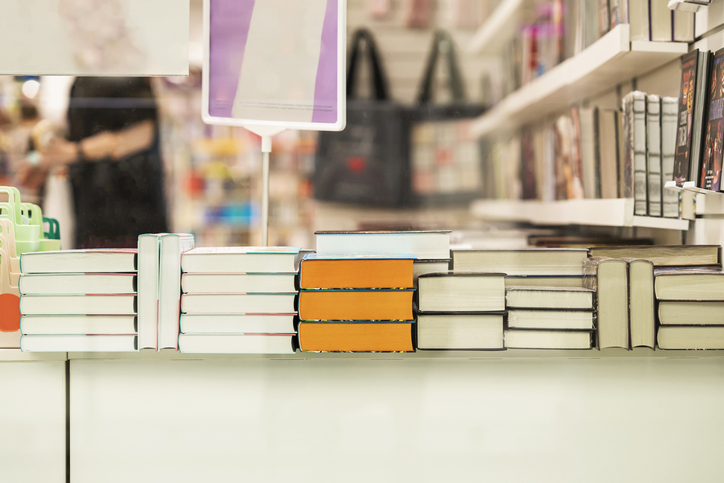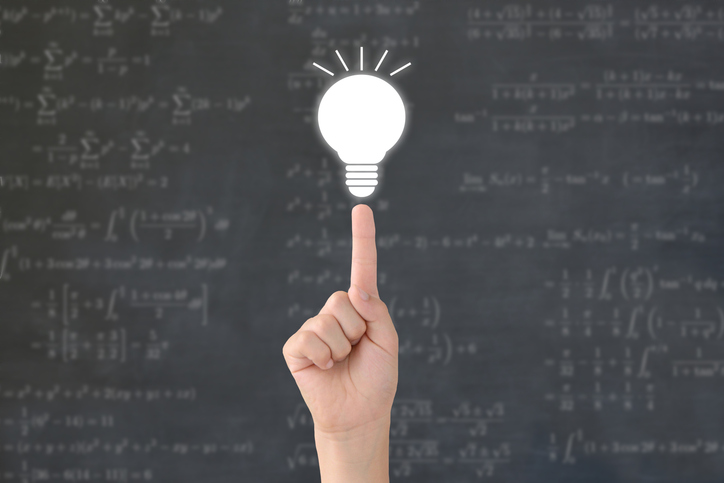2022年10月6日に刊行された『1冊目に読みたいDXの教科書(なるほど図解)』の出版にあたり、出版のきっかけや苦労話などのエピソードを振り返りたいと思います。
今回は、執筆のプロセスについて皆様に共有いたします。
目次
関係者の認識を一致させるため書籍のビジョンを策定する
DXを始める際にビジョンを設計するのと同様、書籍のビジョン設計を最初に実施しました。書籍が何のために存在するのかという点は、まさにパーパスといえるでしょう。特に検索するとDX関連本が数多く見つかり驚かされる今だからこそ、この本が誰にどのような価値を提供するのかについて、関係者間でしっかりと意識を合わせることが重要だと感じました。
今回は、DXの理解が浅い入門者を対象とし、難解な用語は一切避け、必要な用語はすべて解説する方針を採りました。また、DXに取り組る組織では、組織に所属するすべての現場の方にDXを理解してもらうことが成功のポイントでもあるため、本書のターゲットを一般ビジネスパーソンに設定し、誰もが読める書籍として執筆しました。
さらに、視覚的な理解を深めるため、文字情報以上に図解を丁寧に作成し、全ページで文章と図版を並べたレイアウトにしました。
手戻りを最少化するために用語を統一する
書籍内で同じ意味を複数の言葉で表現すると、わかりやすさが大きく損なわれるため、繰り返し登場する用語を統一することにしました。執筆前にすべてを整理するのは難しく、執筆中に書き出した単語も多かったと思います。特に難しいのは、どの用語が読者にとって難解で、どの用語がわかりやすいかを見極めることです。様々な立場の読者を想定しつつ判断しましたが、私たちが普段使い慣れている言葉が一般の方にとってわかりやすいかどうかは判断しづらい部分もありました。そこで、編集者の視点で置き換えるべき言葉を検討していただきました。例えば「レギュレーション」は「法制度」に置き換えられました。
効率よく作業するため構成を決めて手分けする
最初に全員で構成を決めたうえで、執筆部分を手伝ってくれる2名の研究員と分担しました。しかし、全体のトーンや流れを統一するには私一人で仕上げるほうが現実的で、当初いただいた原稿の約8割を私が書き直した印象です。執筆を分担する書籍をよく目にしますが、同じ内容が複数の章で重複したり、用語が統一されていないなどの問題が生じています。本書はDXに関する知識を体系化することを目的の一つとしているため、全体の流れや構造を把握しつつ進めることが不可欠です。その意味でも、大規模な分担作業は適していないと感じました。
全体を通したポンチ絵の位置づけを検討する
テキストを書き始めてすぐ、全ページに入れるポンチ絵の意図について考えさせられました。目的によって用意すべき図がまったく異なるからです。ポンチ絵の位置づけとして、以下のパターンを想定しました。検討の結果、教科書的な書籍という性質を踏まえ、①「文章の内容を抽象化し、わかりやすくする図案」を主体とし、読者の理解を深めるために②~⑤の図案を補完的に追加することに決めました。
- 文章の内容を抽象化し、わかりやすくする図案
- 文章の内容を具体化し、詳しく理解するための図案
- 文章の内容を事例紹介の形で裏付けるための絵
- 文章の内容の根拠となるデータやグラフ
- 文章の内容を可視化するための、顧客行動などのイラスト
紙面に収めるために執筆した文章をスリム化する
各章や各項に割り当てられる文字数は、本書の場合1ページあたり最大約800字です。実際に書きたい内容を自由に執筆すると、文字数が多い場合は3000字を超えることもあります。ページを2つに分割することも可能ですが、いかに約800字までスリム化するかは難しい作業でした。このページで何をしっかり伝えるべきか、どの情報を他のページに回してもよいのか、あるいは本書に含めなくてもよいのかを議論しながら、文字数削減に工夫を凝らしました。
ページ間で執筆内容が重複する課題と格闘する
それぞれのページに重要だと思うことを書いていくと、複数のページで同じ内容や類似した内容を記載してしまうことがあります。一般的な企画書ではそれほど大きな課題にはなりませんが、本書はページ数が200ページ近いため、「どこかで触れたような気がするが、はっきり思い出せない」という状況が起こりました。さらに、ファイルをページごとに分割しているため全体検索ができず、このような場合に非常に困りました。
また、一度執筆した内容でも、文字数の都合で削除したり変更したりすることがあるため、何をどこに書いたかを人の記憶だけで管理するのは非常に難しく、大きなストレスとなりました。
図案やデータの参照元を確認する
図案やデータには参照元がある場合があります。他社のホームページからの引用やデータの出典は原典を記載しましたが、その原典のさらに上位出典がある場合や、複数サイトが出典となっている場合など、表記には悩みました。また、用意したグラフの一部に誤りがあるのではないかと気づき、原典を確認したところ当該グラフは原典と一致していました。しかしよく調べると、原典のグラフ自体に誤りがあることが判明し、その元となる海外データにアクセスして正しいデータを入手し、グラフを作り直す作業も発生しました。本書の流れに大きな影響はありませんが、誤りに気づくと修正せざるを得ず、手間がかかったことを覚えています。
事例紹介の画面イメージや含まれるロゴは、基本的に掲載を避ける方針としました。出版物は一度発行すると修正が難しいため、ここは厳格に判断する必要があると感じました。
様々な場所で執筆する
クラウド環境を活用したため、執筆場所は日本各地に分散しました。契約しているWeWorkの各拠点をはじめ、移動先ではコワーキングスペースやホテルのラウンジ、カフェなどを利用して執筆しました。拠点ごとに設備は異なりますが、特に貸出用モニターがある場所は大いに助かりました。目次や他のページを確認しながら執筆したり、本文をコピペで編集したりする際は、画面数が多いほど効率的です。また、電子レンジはもちろん、ご飯や簡単なおかずまで用意されているコワーキングスペースもあり、全国各地でさまざまな執筆環境を体験できました。
執筆全体の流れとスケジュールを振り返る
執筆期間1年間のおおよその内訳は以下のとおりです。開始当初は何月ごろが忙しくなるか戦々恐々でしたが、まったく予想は外れ、最後の最後が圧倒的に多忙となり、分単位での確認が必要なほどでした。
2021年9月~10月
書籍のターゲット、ビジョン策定、関係者の認識合わせ、執筆に使うツールの選定、全体構成とインデックス作成、執筆分担などをエイヤで決定し、書きたいことを構想する日々。
早ければ2022年4月ごろに出版したいという希望的観測を立てました。
2021年11月~2022年4月
インデックスに沿って文章と図案を一通り書き上げました。ただし、他の業務が優先した結果、執筆の時間が途切れがちで、間があくと何をどこまで書いたか忘れるため、効率が落ちるのを感じました。
2022年4月という目標に対しては、ずるずると先延ばしせざるを得ない状況でした。
2022年5月~6月
出版社から本格的に巻きが入り始めるとともに、第一稿が終了。引き続き見直し(2周目)に入りました。各ページ単位ではしっかり書いたつもりでも、時間をかけて執筆した分、ページ間の整合性や過不足が気になり、大量の書き直しが発生しました。
9月中旬刊行と決定され、その後のスケジュールが詳細化しました。
2022年7月
大量の書き直しによって生じた新たな問題や整合性の課題に対処しつつ、事例の入れ替えや用語の統一を含めて3周目の見直しを実施しました。
Amazonで予約注文が開始されたため、関係者の緊張感が高まると同時に、周囲から応援の声も多くいただき、執筆の優先度が他の業務を圧倒しました。かなりの時間を執筆に投入し、その後、出版日が10月6日に確定しました。
2022年8月~9月
コラムなど本章以外を執筆しつつ、本章の校正を開始。校正はファイルにコメントを入れる形式で行ったため作業効率は下がりましたが、紙面に近いイメージを確認しながら、最後の気力で乗り切りました。
初版発行部数が5500部と決定し、デジタル付録の整備も進めました。
全体を通しての感想など
かなりの時間を投入して執筆しましたので、少しでも読者のお役に立てれば光栄です。最初は執筆作業全体の進め方や課題が見えていなかったため、最適化に時間を要しましたが、印刷側の作業など全体を見渡したうえで、最適な執筆プロセスを設計する要素がいくつか見えてきたように感じます。
本書は単に書籍として読んでいただくだけでなく、読者の皆様にすぐに使えるツールや復習に便利な理解度チェックテスト、筆者による解説動画などを読者付録として用意し、皆様が単に「知る」だけでなく「わかる」「できる」に到達できるよう工夫しました。そのあたりのデジタルな仕掛けについては、別のブログで記載させていただきます。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所
代表取締役/DXエバンジェリスト
DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。
詳しいプロフィールはこちら