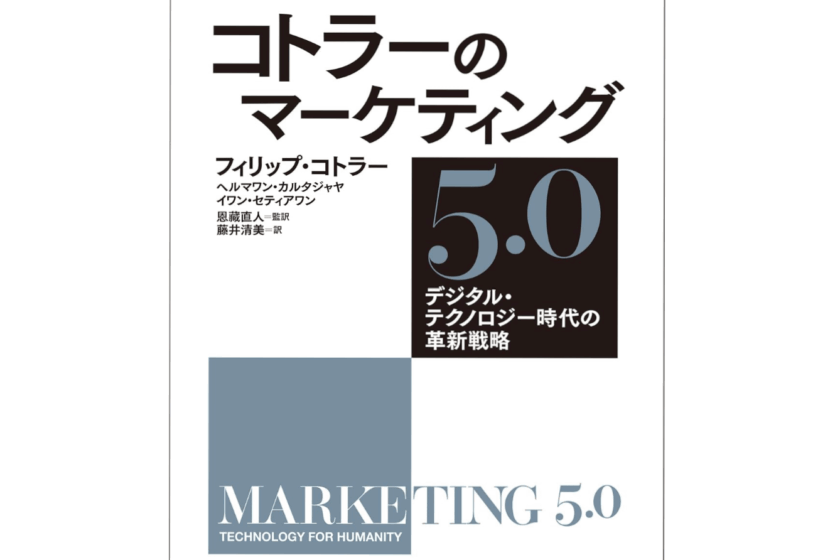フィリップ・コトラーらの著書『コトラーのマーケティング5.0 デジタル・テクノロジー時代の革新戦略』は、最新テクノロジーをTechnology for Humanity(人のための技術)として活用する視座を提示します。本記事は書籍の内容解説を主軸に、章構成の狙いと「五つの構成要素(第8〜12章)」を短時間で把握できるように整理しました。まず本書が何を語っているのかを正確に掴み、そのうえで実務に引き寄せて読むための道しるべを提供します。
目次
本書の基本情報と主題(誰に向けた本か)
本書はフィリップ・コトラー、ヘルマワン・カルタジャヤ、イワン・セティアワンの共著で、日本語版は朝日新聞出版から刊行されています。原著はTechnology for Humanityを副題に掲げ、社会課題と顧客体験の両立を軸に、戦略から戦術までを体系化しています。読者は、テクノロジーの導入そのものが目的化しがちな現場で、顧客価値を中心に据え直すための基準を得られます。
- 社会的分断や世代差、デジタル・ディバイドを前提条件として扱う。
- 組織・データ・プロセスの準備度を点検し、先端技術の活用原則を示す。
- 最終章群で「データドリブン/予測/文脈適合/拡張/アジャイル」を要素として解説。
1.0〜5.0の系譜:進化の要点
マーケティングは段階的に焦点を移しながら発展してきました。本書はこの流れの延長線上に5.0を位置づけます。
- 1.0(製品中心):大量生産・機能優位で差別化。
- 2.0(顧客中心):セグメンテーションとニーズ充足を軸に最適化。
- 3.0(人間中心):価値観や社会性に応える企業姿勢を重視。
- 4.0(デジタル移行):オンラインとオフラインの統合、つながった顧客への適応。
- 5.0(人のための技術):AI等の先端技術を実装し、予測と個別化で体験価値を高める。
五つの構成要素:第8〜12章のポイント
第8〜12章は、技術活用を「規律」と「アプリケーション」で整理します。現場では、人は解釈と共感を、機械は大量処理と予測を担い、役割分担で価値創出を高めます。
データドリブン・マーケティング(第8章)
全接点のデータを識別・統合・活用し、意思決定をデータ起点に切り替えます。品質・同意・ガバナンスを伴うデータエコシステムが前提であり、分析結果を施策や体験に接続する運用まで含めて設計します。
予測マーケティング(第9章)
獲得・離脱・需要などを確率的に先読みし、配分やクリエイティブを事前に最適化します。入力データの設計と検証プロセスの継続運用が成功の鍵になります。
コンテクスチュアル・マーケティング(第10章)
行動・場所・時間などの文脈を踏まえて、状況に適合した体験を提供します。リアルタイムのシグナル取得と意思決定の自動化を両立させ、ユーザーにとって“ちょうど良い”タイミング・チャネル・提案を設計します。
拡張マーケティング(第11章)
テクノロジーで人の価値提供を拡張します。営業・接客・サポートを支える支援UIや、自己解決を助けるナレッジ基盤など、人と機械の役割分担を再設計します。
アジャイル・マーケティング(第12章)
短いサイクルで仮説検証を回し、学習を組織の標準リズムにします。計画一括型からの転換により、不確実性下でも価値仮説を磨ける体制を築きます。
本書の読み方のコツ(実務の視点で要点をつかむ)
はじめに、第2〜4章で示される世代間ギャップ/富の二極化/デジタル・ディバイドを自社の前提に照らして整理します。次に第5〜7章の戦略編で、組織の準備度・ネクストテックの理解・顧客体験設計を確認し、最後に第8〜12章の五要素を自社のユースケースへ接続すると理解が深まります。
背景知識の整理には、当サイトの基礎記事が有用です。環境・競争の把握には環境分析フレームワーク、価値提案づくりにはリーンキャンバス、資源配分や施策の具体化には経営資源シフトや問題解決プロセスをご参照ください。
まとめ
マーケティング5.0は、テクノロジー偏重ではなく人のための技術という価値基準で全体設計を行う思想です。本書は、社会課題→戦略→五つの要素の順に学ぶ構成になっており、必要な章から逆引きしても理解が進むように配慮されています。体系的に学びを深めたい場合は、当研究所のDX研修(基礎編/役員向け/AI課題解決編)もご活用ください。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所
代表取締役/DXエバンジェリスト
DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。
詳しいプロフィールはこちら