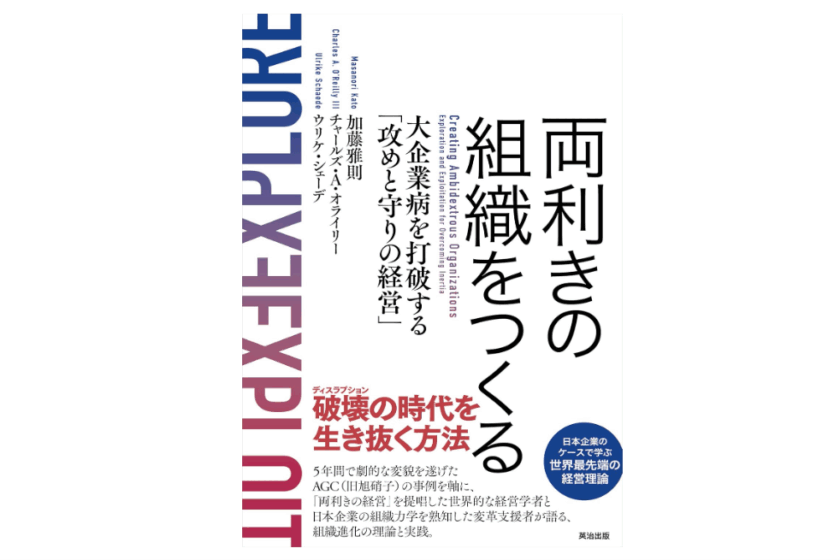「過去の成功体験が足かせとなり、新しい変革が進まない」
「既存事業(守り)と新規事業(攻め)の両立に苦しんでいる」
こうした「大企業病」や「サクセストラップ」は、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する多くの企業が直面する課題です。
本記事では、この課題克服のヒントとなる書籍『両利きの組織をつくる-大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』をご紹介します。
本書で詳細に解説されているAGC社の変革事例は、まさにDX推進にも通じる組織変革の実践録です。本記事では、DXの専門家である荒瀬光宏の視点から、同書が示す「アラインメント(整合性)の再構築」や「リーダーシップ」の重要性を読み解きます。
目次
書籍『両利きの組織をつくる』とは(概要)
発行日:2020年3月5日
著者:加藤雅則、チャールズ・A・オライリー ほか
発行所:英知出版株式会社
書籍の構成(目次)
- いま必要な組織経営論
- AGC、変革への挑戦―戦略と組織を一体として変える―
- 両利きの経営―成熟企業の生き残り戦略―
- 組織はどのようにして変わるのか―アラインメントの再構築―
- 組織開発の本質―トップダウンとボトムアップの相互作用を作り出す―
- 脱皮できない蛇は死ぬ―日本企業のための組織進化論―
「大企業病」や「サクセストラップ」に悩む経営層・DX担当者へ
本書は、両利きの経営と組織を、AGCという日本の伝統的企業をテーマに、事例・理論・実践の三要素を踏まえて解説しています。素材産業を中心とする日本の伝統的企業の経営者や役員の皆さま、またDX推進を担うリーダーの皆さまにぜひお読みいただきたい一冊です。
素材産業はコンシューマーから遠く、DX戦略やコトづくりのテーマで悩んでいる企業も多いと存じます。絶対的なデジタル戦略が見えない場合でも、新しいイノベーションを生む組織能力をどのように実現するかを考える際に、本書は大いに参考になるはずです。
書評:AGCは「両利きの組織」をどう実現したか
「サクセストラップ」の克服とAGCの変革
両利きの経営が着目するサクセストラップとは、過去の成功体験から導かれたKSF(成功の鍵)に沿って組織やガバナンス、文化が形成され、新しい環境に適応できなくなる状態を指します。この課題はDX戦略とも共通しており、DXと両利きの経営の比較については前回の書評(『両利きの経営』)をご参照ください。
今回は、両利きの組織を実践した事例として、日本の素材産業大手であるAGC株式会社を取り上げています。実際に同社の変革を支援した著者ならではの視点で、具体的な打ち手が詳細に紹介されています。素材産業は多くの顧客が存在し、特定の最終顧客を絞りづらいため、DX戦略の立案が困難になりがちです。AGC社はDX戦略で全社を一斉に推進するのではなく、両利き経営によってイノベーションが生まれ続ける組織への変革を行いました。既存事業の深化も疎かにせず、探索と深化を両立させた点で、このコンセプトが適合していたと考えます。
同社は「自らがイノベーションを起こす会社」ではなく、「顧客のイノベーションを加速する製品・素材をつくる会社」へと方向性を定め、経営陣がリーダーシップを発揮して変革を実行しました。このビジョンは企業ステートメント「Your Dreams, Our Challenge」に反映されています。
変革の鍵:「アラインメントの再構築」とは
本書で頻出する「アラインメント」(戦略や組織の整合性)は、DXビジョンの整合性と同様の役割を果たします。深化型事業と探索型事業それぞれのあるべき姿を設計し、両事業のアラインメントを行い、両組織間で発生しやすいコンフリクト(対立・摩擦)を経営主導で解決・調整する仕組みを構築しています。これらの手法は、DXを推進する企業にとっても学ぶべき重要なポイントです。
実行の鍵:「トップの覚悟」と「現場の意識変革」
本書『両利きの組織をつくる』で示されたAGCの変革は、経営陣のリーダーシップによる「トップダウン」の組織構造改革(攻めと守りの分離・統合)の好事例です。
このような大規模な変革を成し遂げるには、トップの強い覚悟が不可欠です。しかし、その「トップの覚悟」や「ビジョン」を、どうやって現場の社員に浸透させ、実行に移すのでしょうか?
当研究所がご支援した株式会社ユニマットリック様の事例も、小松社長の「全体最適」というビジョンを、強力な「トップダウン」で推進した変革のケーススタディです。
ユニマットリック社では、変革のキックオフとして当研究所の「DX基礎研修」を活用されました。その目的は、専門家の口からトップダウンの重要性を理論的に伝え、全社員の意識を変革の方向へ揃える「共通言語」を育むことでした。
AGCの事例が「両利き」という組織の「型(構造)」を変える話だとすれば、ユニマットマットリック社の事例は、その型を動かすための組織の「意識(マインドセット)」をどう変革するか、という実践的なヒントを与えてくれます。
(トップダウン型DXの成功条件については、こちらの記事でも詳しく解説しています。)
どちらの変革も、トップのリーダーシップと、それを「自分ごと化」する現場の行動変容なくしては実現し得ません。
まとめ:変革に必要なリーダーシップと組織開発
本書の目次にもある「脱皮できない蛇は死ぬ」という言葉は、まさにDX時代の組織変革の必要性を示しています。AGC社の変革は経営陣のリーダーシップなくして実現し得ませんでした。しかし、組織開発は「変える」のではなく、組織が「変わる」ことを支援する取り組みです。変革の主役は現場のすべての社員であり、経営者がその責任を果たしつつ、社員一人ひとりのモチベーションを理解し、行動変容をデザインした事例として、本書は大変示唆に富んでいます。過去の成功とそこから学んだKSFだけに執着せず、変革の難しさを理解して逃げずに立ち向かい、新しい環境で価値を高められる真のリーダーシップを持つ経営者と企業が増えることを心より願っています。
DX推進と組織変革にご関心のある方へ
本書で示されたリーダーシップやイノベーションを生む組織づくりは、DX推進の中核です。デジタルトランスフォーメーション研究所では、DX推進のための研修プログラムを提供しています。
- 経営層向けDX 研修|役員・幹部のためのDXビジョン・戦略策定ワークショップ
AGCやユニマットリック社のように、トップダウンで変革を主導する経営層・役員向けの研修です。 - 新規事業開発のためのDX研修(価値創造DX研修)
「両利きの経営」の「探索(新規事業)」を担う、DXリーダー向けの研修です。
参考文献・出典
- 加藤雅則『両利きの組織をつくる――大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』(2020年3月)

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所
代表取締役/DXエバンジェリスト
DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。
詳しいプロフィールはこちら