学びにおけるアウトプットの重要性
変化の激しい時代こそ、大人も子供も学ぶ意義が高まります。しかし、人間の脳はインプットした情報を使わないと徐々に忘れてしまう特性があります。したがって、アウトプットはインプットの効果を最大化するための唯一かつ最も有効な手法です。
アウトプットには多様な形があります。子どもなら日記を書く、夏休みの自由研究をまとめる、何か作品を制作するといった方法が考えられます。本人のモチベーションが高まり、より深く掘り下げたいという意欲が生まれるものであれば何でも構いません。大人であれば、書籍やブログで文章を執筆する、ノートに整理してまとめる、プレゼンテーションを行う、動画を作成してYouTubeやUdemyに公開するなど、多彩な手段が選べます。
アウトプットを行うと「なぜそうなるのか?」「別のケースではどう違うのか?」といった疑問が生まれます。これを調べて裏付けを取ることで、学びはさらに加速されます。かつてのように図書館で時間をかけずとも、インターネットを使って短時間で必要な情報を収集できる現代では、アウトプットに必要な調査に膨大な時間はかかりません。
インプットの効率も高まる
アウトプットを前提に学習を進めることで、情報をただ受け取るだけでは得られない効率的なインプットが可能になります。
具体的には、フレームワークに沿ってインプット内容を構造化・具体化・抽象化する意識が働き、理解が深まり定着しやすくなります。たとえば、講演を聴く際にアウトプットを想定すると、自然と不明点や疑問が生じ、終了後に講演者へ質問してその場で不足部分を補完できるようになります。
超高速PDCAを回せる
ビジネススクールで学んだ手法は、習得した翌日には職場で実践し、うまくいかない点があれば次回の授業で講師に確認するといったサイクルを回すことで、学びを最大化できます。
この超高速PDCA(またはOODA)アプローチは、不透明な環境下での事業開発にも有効です。実践の成功・失敗にかかわらず、次回のインプットへの意欲が高まり、学びのモチベーションを維持できます。
学校教育でもアウトプットの機会を増やしたい
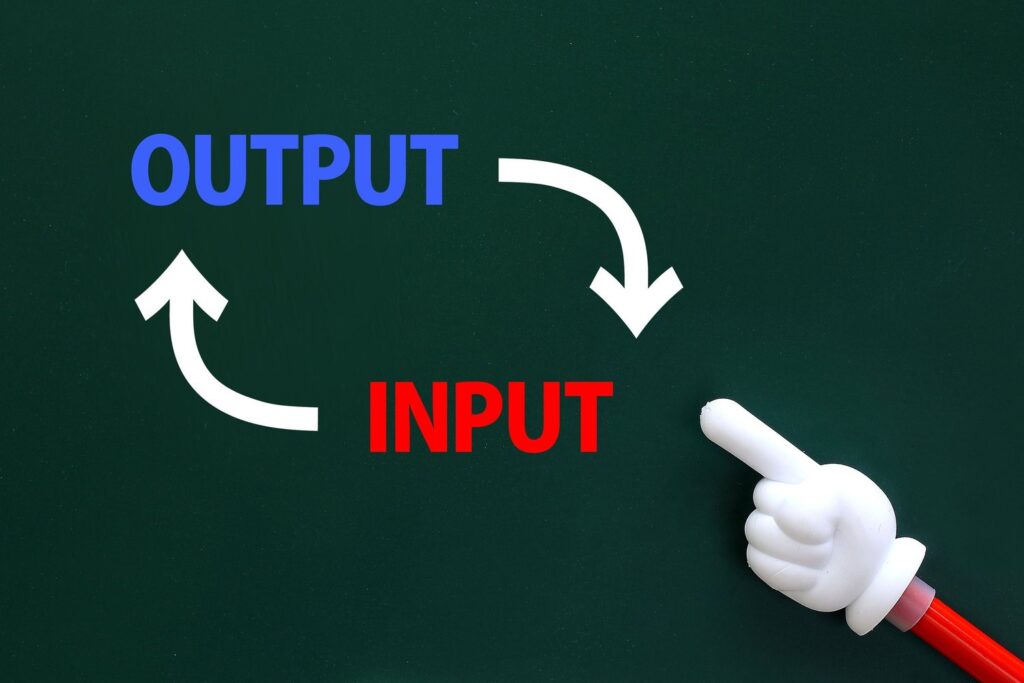
学校教育では、「あの学びは実社会で必要だった」と気づくのが遅れがちです。長期間学んだ後に社会に出ると、学んだ内容を忘れるだけでなく、最新の知見と乖離したり、誤りが明らかになる場合もあります。
こうした課題を克服するには、教育現場でも「学び→実践→振り返り」のスパイラルを取り入れる必要があります。実社会での実践を通じて学びを深めるサイクルを導入しなければ、日本の競争力は低下し続けるでしょう。
近年、「アクティブラーニング」が注目されていますが、学習指導要領に縛られるカリキュラム改革には限界があります。一方、学習指導要領外で運営されるフリースクールのような選択肢もありますが、伝統的な教育観が根強い日本では、保護者が非従来型教育を躊躇するのも理解できます。
しかし、日本の未来に向けては、教育制度を大胆に変革し、即効性のあるアウトプット機会を提供できるリーダーの登場が不可欠です。
アウトプットしながら生きる
これからも変化が続く環境下では、人は学び続ける必要があります。学ばずに遂行できる仕事は機械に代替される可能性が高いため、自己の興味分野を見つけて知識を深め、アウトプットの機会を通じて学びを社会に還元する生き方が求められます。
アウトプットの場を見つけたら積極的に参加し、その経験を自らの成長の糧にすることが重要です。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所
代表取締役/DXエバンジェリスト
DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。
詳しいプロフィールはこちら




