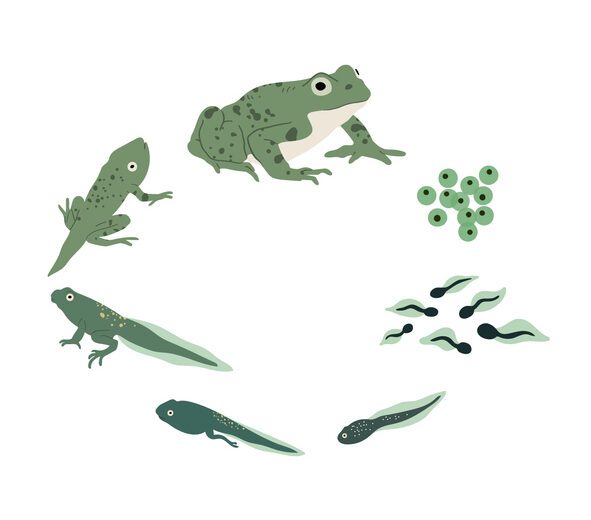年末が近づくと、B2B業界で毎年行われてきた「カレンダー配り」。しかし、リモートワークの普及や効率化の観点から「カレンダー配りは無駄ではないか?」という疑問の声も高まっています。確かに、非効率な側面があるのは事実です。
本記事では、このカレンダー配りが「無駄」と言われる理由と、それでもアナログ時代になぜ「儀式」として存在し続けたのか、その背景と目的を5W1Hで分析します。
そして、この一見非効率な慣習の本質を理解することこそが、実はDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の鍵である理由を考察します。アナログ文化の背景を知り、DXに必要な「人間理解」のヒントを得ることができます。
目次
カレンダー配りは「無駄」なのか?
「カレンダー配り」という慣習は、多くの企業で長年続いてきましたが、近年その是非が問われています。まずは「無駄」とされる主な理由を整理します。
非効率・高コストという「無駄」
最も大きな理由は、非効率性とコストです。カレンダー自体の制作費や印刷費に加え、それを配布するために営業担当者が顧客先を訪問する時間(人件費)や交通費が発生します。
特に年末の多忙な時期に、営業担当者がカレンダーを配るためだけにアポイントを取得し、移動することは、生産性の観点から「無駄」と指摘されても仕方ありません。また、受け取る側も不要なカレンダーの処分に困るケースもあり、SDGsの観点からも資源の無駄遣いとの見方があります。
デジタル化・リモートワークと逆行する「無駄」
働き方の変化も大きな要因です。テレワークの普及やフリーアドレス化により、オフィスの在席率が低下し、訪問しても担当者に会えないケースが増えました。また、オフィスの縮小に伴い、壁掛けカレンダーの掲示場所がなくなるなど、物理的な需要も減少しています。
こうした状況は、従来のアナログな業務プロセスが、現代のデジタルな働き方と適合しなくなっている典型例と言えます。デジタル化の本質は、単に紙をデータに置き換えることではなく、業務プロセス全体を見直すことにあります。
アナログとデジタルの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ デジタルとは?意味をわかりやすく|アナログとの違い・語源・ビジネスでの使い方【図解】
「カレンダー配り」とはどんな儀式だったのか(5W1H)
では、なぜこのような「無駄」とも言える儀式が、アナログ時代には必要とされ、脈々と受け継がれてきたのでしょうか。その実態を5W1H(いつ、どのように、どこで、誰が、何を、何のために)で分解し、当時の「儀式」としての側面を考察します。
いつ(WHEN)・どこで(WHERE)
この儀式のピークは12月上旬から年末です。基本的には12月末までに渡すという暗黙のルールがありました。

会議室での年末挨拶イメージ
受け渡し場所は、会議室での打ち合わせの最後が最も格式が高いとされ、それが叶わない場合はロビーや受付付近、最終手段として郵送が選ばれました。「年末の挨拶」と称して打ち合わせを設定すること自体が、儀式の一部でした。
どのように(HOW)・誰が(WHO)
「カレンダー配り」にはお作法と言葉の流れがありました。
「今年も早いもので」「来年もよろしくお願いいたします」「よいお年を」といった一連の挨拶と共にカレンダーを手渡します。

あいさつ回りをする上司と部下のイメージ
主に営業部門が顧客や取引先に配布し、当日は上司と部下のペアで臨むことも多く、配布計画の管理も重要な業務でした。
最大の目的:何のために(WHY)
配布する「モノ」はカレンダーですが、この儀式の本当の目的(WHY)は別にありました。それは、〈今年のプロジェクトの進捗確認と次年度活動計画のヒアリング〉です。
カレンダー配りを口実にアポイントを取り、対面の場で「当年度の予算消化」や「組織・人事異動情報」など、デジタル(メールやチャット)ではスルーされやすい重要な情報を引き出すことが、この儀式の主目的だったのです。
アナログの「目的」をDXでどう再設計するか
カレンダー配りという「手段」は、現代において非効率(無駄)かもしれません。しかし、それが果たしていた「目的(WHY)」、すなわち「対面での関係構築」や「次年度予算のヒアリング」は、ビジネスにおいて今も変わらず重要です。
DXとは、こうしたアナログ時代に培われた業務の「目的」を理解し、デジタル技術を用いて現代に最適化(再設計)することに他なりません。
アナログの優位性を理解する
重要なのは、対面で情報収集を行うことの優位性を理解することです。どれだけデジタル化で効率化しても、アナログの強みを理解し、必要に応じてアナログ的手段を設計に組み込むことが求められます。
OMO(Online Merges Offline)のように、デジタルでサービス全体を包み込む中で、アナログの優位性を活かすポイント(例えば、重要な商談はあえて対面を選ぶなど)を慎重に設計することが重要です。単に「無駄だから」とアナログを全廃するだけでは、かえって顧客との関係性が希薄になる可能性もあります。
DXの本質は「人間理解」
カレンダー配りを単に「無駄」として廃止し、メールでの挨拶に切り替えるだけでは、本質的なDXとは言えません。その儀式が満たしていた顧客や営業担当者の「インサイト(人間理解)」を汲み取ることが重要です。
例えば、「年末に対面で話したい」という顧客の潜在ニーズを理解し、それをWeb会議や効率的な情報提供といったデジタル手段でどう代替・昇華させるかを考えること。それこそがDXの本質です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義や本質については、こちらの記事もご参照ください。
→ DXとは?(デジタルトランスフォーメーション)をわかりやすく解説【2025年版】
第四次産業革命の過渡期に必要な視点
現代は、第四次産業革命の過渡期であり、顧客も働き手もアナログな存在とデジタルな仕組みが混在しています。この時期の競争原理を考えるには、デジタル設計とアナログ配置の最適バランスを検討することが鍵となります。
重要なのは、カレンダー配りのようなアナログな儀式の「目的」を理解し、それをデジタルサービスや施策でどのように再現・再設計するかを考えることです。単に生産性の低いアナログ時代を笑うだけでは、本質的な洞察は得られません。DXにおいて真に必要なのは、技術理解だけでなく「人間理解」なのです。
第四次産業革命と、過渡期における競争戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。
→ 第四次産業革命とKSF解説―データ×高速PDCAで顧客価値を創る
まとめ
本記事では、年末の「カレンダー配り」が無駄と言われる理由と、その背景にある「儀式」としての目的をDXの視点で考察しました。
- カレンダー配りは「非効率・高コスト」「デジタル化との逆行」の面で無駄と指摘されています。
- 一方で、アナログ時代には「次年度計画のヒアリング」や「対面での情報収集」という重要な目的がありました。
- DXとは、この「目的」を理解し、デジタル技術で現代に再設計することであり、その本質は「人間理解」にあります。
非効率なアナログ業務を見直し、その目的をデジタルでいかに昇華させるか。この視点こそが、第四次産業革命の過渡期におけるDX推進の鍵となります。
自社の「アナログな慣習」を見直す第一歩として、DXの基礎知識を体系的に学んでみてはいかがでしょうか。

株式会社デジタルトランスフォーメーション研究所
代表取締役/DXエバンジェリスト
DX推進・企業変革の専門家。豊富な現場経験と実践知をもとにコンサルティング、企業研修、講演活動を行う。
詳しいプロフィールはこちら