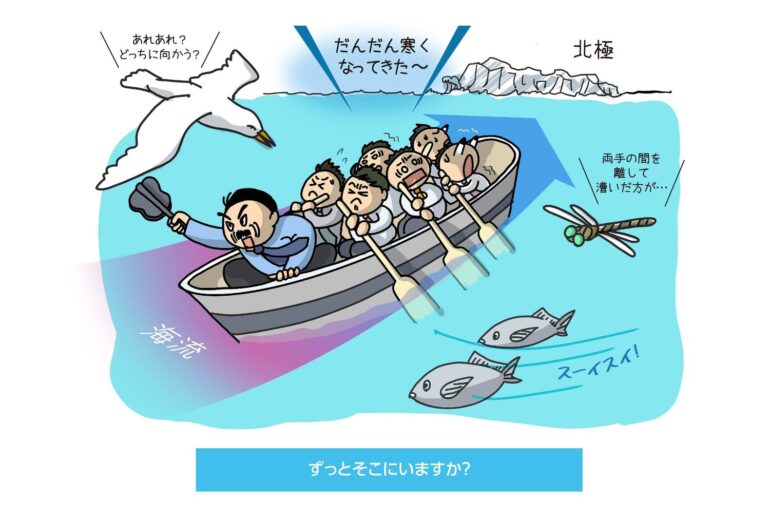DXを進めるには、DXフレームワークで考えを整理することが役に立ちます。本記事では、デジタルトランスフォーメーション研究所の関連記事をまとめ、DXフレームワークの全体像を短時間でつかめるようにしました。まずは自社の目的に近いテーマからお読みください。
DXの前提知識:3段階フレームワーク
デジタイゼーション/デジタライゼーション/DX(3段階モデル)
DXを成功させる第一歩は、デジタル化の段階(デジタイゼーション → デジタライゼーション → DX)を正しく理解することです。情報のデータ化、業務プロセスの変革、そして事業モデルそのものの変革を区別せずに進めると、期待した成果が得られません。自社が今どの段階にあり、次にどこを目指すべきかを明確にすることで、活用すべきフレームワークも定まります。
組織の「共通言語」を作る(研修)
DXを特定の部署だけでなく組織全体で加速させるには、全社員が同じ物差しを持ち、共通言語で話せることが不可欠です。本質を捉えたリテラシー教育が、変革への心理的ハードルを下げ、自律的な改善を生みます。
1. DX戦略策定と経営資源
DX戦略の立て方(3ステップ策定プロセス)
DX戦略の策定プロセスを実践的な3ステップ(現状分析→戦略策定→組織変革方針)で解説します。マネジメント層が主体となり、現状分析から具体的な戦略(Who/What/How)、組織変革までを一気通貫で設計する流れをつかめます。
DX戦略の立て方とは?マネジメント層向け実践3ステップと策定プロセスを解説
DX戦略のための環境分析:PEST・3C・SWOT・T2C
戦略策定における環境分析は、自社が戦う土俵(ドメイン)を決めるために行います。外部環境(PEST)の変化をTechnologyの視点(T2C)で捉え直し、競合や顧客(3C)との関係性を整理します。クロスSWOTで自社の強みをどこにぶつけるかの優先順位をつけることで、実行力のある戦略へと落とし込めます。
環境分析フレームワーク5選:PEST・3C・5F・SWOTとDXへの応用
DX時代の経営資源シフト(ヒト・モノ・カネ → データ・コト・ジカン)
これまでの経営資源(ヒト・モノ・カネ)に、DX時代の鍵となるデータ・コト(体験)・ジカンを掛け合わせる考え方です。データを知見に変え、顧客体験(コト)に投資し、学習と回収のサイクル(ジカン)を速めることで競争優位を築きます。
「ヒトモノカネ」フレームワークとは?DX時代の経営資源シフトも解説
部分最適と全体最適
DX推進において「部門ごとの効率化」が「全社的な足かせ」になるケースは少なくありません。なぜ部分最適の罠に陥るのか、その原因を整理し、デジタル技術を活用して全体最適へと移行するためのポイントを解説します。
鳥の目・魚の目・虫の目フレームワーク
「目指す姿」を捉える鳥の目、市場やトレンドの流れを読む魚の目、現場の課題を深掘りする虫の目。この3つの視座を自在に行き来することで、DXにおける意思決定の精度を高めます。会議やプロジェクトの振り返りにも有効な視点です。
自社に合わせて実践する(研修)
2. 新規事業創出と価値創造
DX新規事業創出のプロセス
既存事業の枠を超え、新しい価値を生み出すための全工程(探索→課題設定→ビジネスプラン)を解説します。環境分析で市場の「隙間」を見つけ、顧客の深い理解から解決策を導き出す、DX時代に求められる新規事業の勝ちパターンを整理しています。
DX新規事業創出の全プロセスを解説|大企業向けフレームワークとAI活用法
新規事業のための環境分析:市場機会の特定
新規事業における環境分析は、未充足のニーズや「勝てる勝機」を見つけるための探索ツールです。3C分析で競合が手を出せていない領域を特定し、PEST分析で将来的な追い風を確認します。戦略策定時とは異なり、より「機会の導出」に特化した視点で活用します。
環境分析フレームワーク5選:PEST・3C・5F・SWOTとDXへの応用
リーンキャンバス:DXの価値仮説を1ページで検証
ビジネスモデルの核心を9つのブロックで可視化します。不確実性の高いDX新規事業において、仮説を素早く書き出し、検証結果に基づいてアップデートし続けるために最適なツールです。
第四次産業革命とKSF(成功の鍵)
データを集め、分析し、現場へフィードバックする「高速な学習循環」こそが、第四次産業革命以降の競争力の源泉です。この循環を支えるためのKSF(重要成功要因)を理解することで、本質的な価値創造の仕組みを構築できます。
第四次産業革命とKSF解説―データ×高速PDCAで顧客価値を創る
自社に合わせて実践する(研修)
3. 問題解決とAI活用スキル
問題解決のプロセス:What→Where→How
すべての変革の基礎となる問題解決のステップを解説します。「何が問題か(What)」「どこに原因があるか(Where)」「どう解決するか(How)」の順序を徹底することで、生成AIを最大限に活用したスピーディーな解決が可能になります。
問題解決のプロセスとは?基本3ステップとDX時代のフレームワーク
MECE(ミーシー):生成AI時代の思考構造化スキル
「漏れなく、ダブりなく」情報を整理するMECEは、DX推進における複雑な課題整理の必須スキルです。特に生成AIとの対話において、前提条件や検討範囲をMECEに指定できるかどうかで、アウトプットの質が大きく変わります。
MECE(ミーシー)とは?具体例で学ぶ基本と生成AI時代の思考構造化スキル
自社に合わせて実践する(研修)
まとめ|自社に合うDXフレームワークを見つける
本記事では、DX推進の土台となる「DX戦略策定と経営資源」、具体的な「新規事業創出と価値創造」、そして全ての基盤となる「問題解決とAI活用スキル」の3つの側面から、役立つDXフレームワークを整理しました。
DXの推進には、フレームワークの知識を組織に定着させ、実践できる人材を育てることが不可欠です。デジタルトランスフォーメーション研究所では、本質を学びAIを活用した実践までを体験する「DX研修サービス」を提供しています。自社の状況に合わせた最適なプログラムをぜひご活用ください。